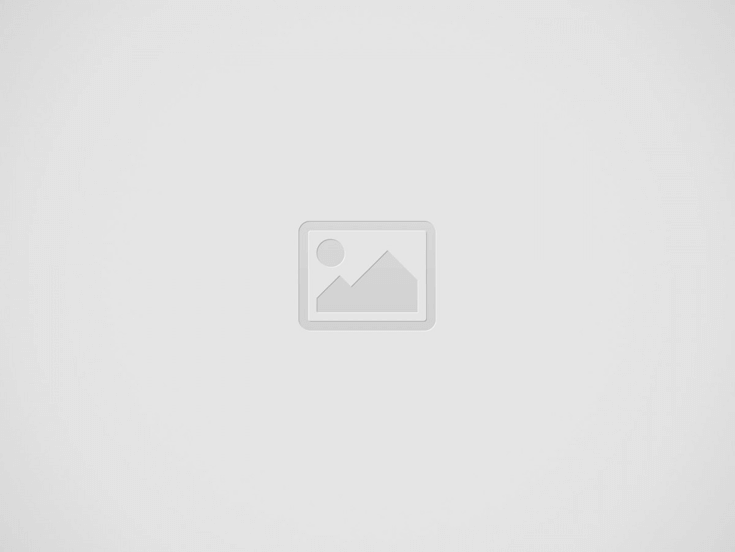この緊急性の高さは、子供たちが資本主義のイメージに少しニュアンスを与える物語に参加できることを条件として、全国の高校の授業で「善」を必修科目にすべきであることを意味する。しかし、ステファン・ヤールの最新エッセイ映画は、決して諦めに変わる恐れのない本物の同情的な怒りを特徴とし、差し迫った災害から私たちを救ってくれると思われる唯一のもの、つまり常識と善良さに訴えます。
「Goodness」では、ステファン・ヤールは、記録的な収入格差を生み出し、大企業の取締役が理性を無視してボーナスを徴収することを可能にする無制限の資本主義に焦点を当てています。経済学者や社会学者へのインタビューは、階級社会の深淵を隠すのに役立ってきた蔓延する消費ヒステリーの同じ真っ暗な状況を裏付けている。それは衝撃的で、皮肉的で、ひどく不公平です。また、描かれているのはかなり一方的な絵でもあります。 「敵側」の代表者、取締役、少なくともベンチャーキャピタリストは発言することを許可されません。そしてもちろん、私たちが「エッセイ映画」というジャンルで活動している限り、ナレーションはドキュメンタリーよりもはるかに討論投稿の形をとる可能性があります。パレットにさらにいくつかの色合いを見たいと思うことを妨げるものではありません。
インタビューには、トム・バーググレンが資本主義の原則と表現形式についてどう考えているかをテキストで説明する、かなり綿密に計算されたシーケンスが散りばめられています。これらの、時にはおしゃべりで、時にはユーモラスな小さな独白やスケッチは、プロの経済学者の棒グラフや計算と対比するとともに、労働者階級の背景を持つ一般人がどのように考え、考えるかを示すものであると想像しています。ベルグレンの証言や物語の多くは読んでいて楽しくて啓発的ですが、ヤールはハサミの使い方をもっと厳しくしたいと思うこともありました。
一方で、「The Goodness」全体で一貫しているのは、過剰に演出され臨床的なものではなく、個人的で普遍的なものであると感じられることです。時折、私たちは胸が張り裂けるほど美しい自然の映像を目にすることがありますが、その作者がステファン・ヤールであることを忘れてしまった場合に備えて、ピーター・アンダーソンのアナウンサーの声が、資本主義の黒い数字に直面したときに生じる憂鬱な感覚に完璧に同調しています。ヤールがカメラを肩から完全に持ち上げて現実に飛び出すことなく、じっと座って何が起こっているのかを受け入れることができなかったという感覚が、「The Goodness」に強さと魅力を与えているのです。
『ザ・グッドネス』の映画ポスターには『ロッキー』の絵が描かれている。この文脈で考えると、マーティン・ケラーマン監督のシリーズのファンではあるものの、「善」についての深刻な主張については何も知らない無知なティーンエイジャーたちが、自分たちが見られると信じて映画館に転がり込んでくる以上に良いものは思いつかない。「ロッキー」白いキャンバスに。それは彼らに失望してもらいたいからではなく、『ザ・グッドネス』をできるだけ多くの人に、できれば完全に警戒が解けたときに見てもらいたいからです。