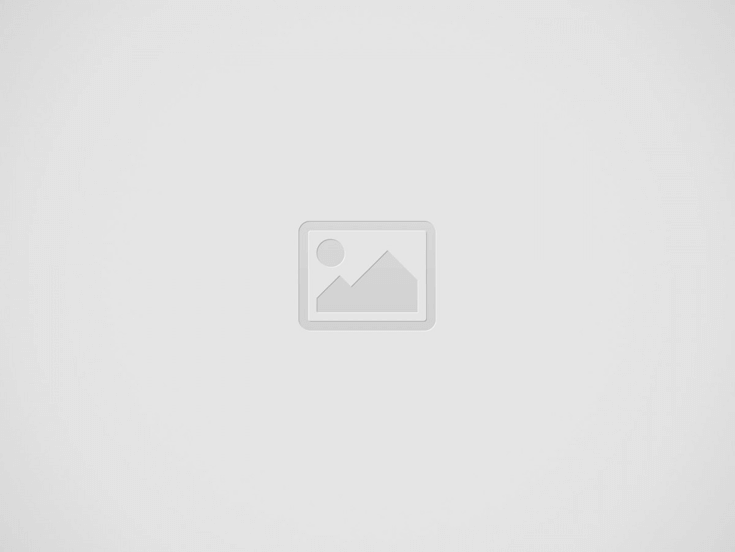新進気鋭のアレハンドロ・ランデス監督は、新作『モノス』ですでに世界各国の映画祭で数々の賞を受賞している。 「地獄の黙示録」やドイツの音楽祭「フュージョン」を彷彿とさせる、最大限のコントラストと音と映像の相互作用による、非常に厄介なドラマスリラー。達人で天才的!
ラテンアメリカの山で、8人の若者が人質、牛、そして大量の武器とともに暮らしている。 「モノス」は、ホルモンの影響で過酷な環境の中で繰り広げられる古典的なサバイバル物語ですが、社会のない人間のロマンスについても描かれています。明らかに「蝿の王」との比較が行われていますが、これは実際にはコピーやリメイクではありません。 「Mono」のビジュアルと舞台言語は刺激的で革新的であり、時には魅惑的に美しいものです。そこには映画の表現全般にわたる監督の意識があり、それが凝縮された小さな幻想的なシーンに貢献している。
この現代的な自己認識の証拠は、アレハンドロにランボーという名前の主人公がいたということです。ランボーはナイフを持っていませんが、ゲリラリーグの中で共感を示す唯一の人物であり、仲間たちほど制限のない荒野での生活に夢中ではないようです。文明を目指す彼女の旅は、人質であるジュリアン・ニコルソンの脱出の試みと、自然の力との残酷な遭遇と並行して描かれています。
近年の流行に敏感な文化が花の香りのする自然のロマンチシズムに縁取られていたとしたら、『モノス』は攻撃的な蚊、汚い急流、血なまぐさい虐殺シーンなどを駆使して、そのイメージを洗い流すために全力を尽くしている。監督は、主人公にランボーという名前を付けることで、この神話を生み出した流行に敏感なオタク文化に直接言及しています。彼は、たとえば「アバター」の基となった高貴な野蛮人と輝きの伝説を武装解除します。
自然と社会との対比は、例えば、夜のパーティーで若者たちが牛にサイリウムを着せたりするなど、細部にまで常に現れています。しかし、増幅された水滴の音もまた、セメントバンカーにいるたった一人の人質が踊るための固定ドラムビートに変わりました。また、ゲリラのリーダーが、凶悪犯と兵士の違いは、若者が上半身裸になるかシャツを着るかどうかにあると指摘するシーンなどでも登場する。あらゆる小さな要素に対するこの感覚が、この映画を常に驚かせています。ランボーがテレビでグミベアの製造に関する番組を見るときのように。
サウンドデザインも印象的で、自明ではなく、ホイッスルや若者/群れが狩りをするときの特別な音などの新しい発明を常に提供しています。すべてのコントラストが最大限に高められており、俳優全員が魔法のような自信を持っているようにも見え、それが輝いています。全体として、それは傑作としか言いようがありません。最後に同じような感情を引き起こしたのは、「シティ・オブ・ゴッド」のときでした。
ストーリーテリング、写真、音楽の両面で驚きをもたらす監督がついに登場します。自然の容赦を1時間40分耐えて、グランピングの意味も分かりました。なぜなら、「Monos」は自然がさまざまな顔を持っていることを決して忘れさせないからです。