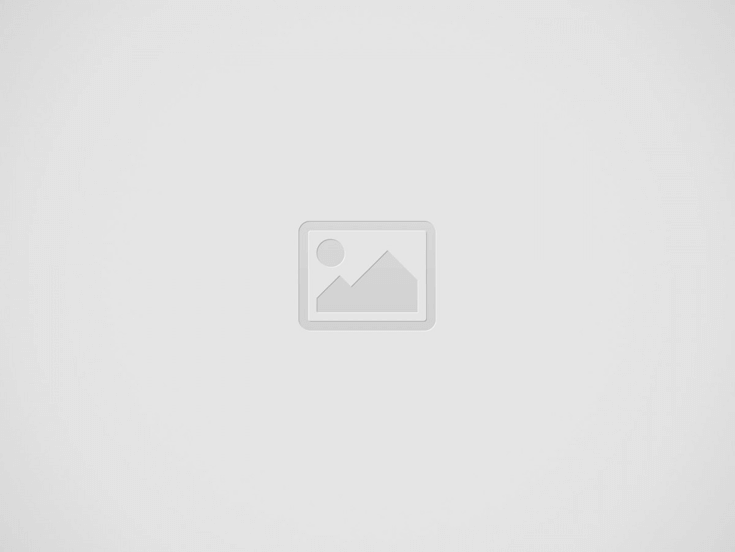「最後の息まで」は、1960 年代初頭にフランスのニューウェーブを始めた映画の 1 つであり、当時画期的だった革新的な作品として今でも最もよく知られています。ジャンプカット、パリの路上でのロケ撮影、そして伝統的なフランスの価値観に対する一般的な軽蔑と軽視の混合により、この映画は duga と呼ばれる時代記録となっています。
「最後の息まで」は、1960 年代初頭にフランスのニューウェーブを始めた映画の 1 つであり、当時画期的だった革新的な作品として今でも最もよく知られています。ジャンプカット、パリの路上でのロケ撮影、そして伝統的なフランスの価値観に対する一般的な軽蔑と軽視の混合により、この映画は duga と呼ばれる時代記録となっています。
ジャン=リュック・ゴダールの最初の長編映画『最後の息まで』には、伝統的かつ保守的な文化的表現を伴うフランスのニューウェーブのあらゆる犯罪が組み込まれている。傲慢な小泥棒が不謹慎にも警官を殺害し、金を手に入れて娘に会うためにパリへ行くというこの物語は、今日の基準からすればさほど物議を醸すものでも革命的でもないが、歴史的、文化的観点から見ると最も重要な物語の一つに成長する。映画 ヨーロッパ映画の歴史。映画がスタジオで撮影され、革新的な思考を志向することのない一般的な衣装ドラマが好まれる傾向にあった当時、『最後の息まで』のような映画はまったく前例がありませんでした。アメリカのポップカルチャーへの明らかなオマージュを込めて、この映画は典型的にフランス的と考えられるすべてのものを打ち破りました。
軽犯罪者ミシェル・ポワカールは、本当の意味でのアンチヒーローである。同情も外の世界への理解もない彼は、万引きから警察による殺人まで、何をしても逃げられると考えているようだ。彼はアメリカ映画を尊敬しており、特にハンフリー・ボガートと彼のハードボイルドな登場人物に憧れています。マルセイユで車を盗んだ後、時折会うアメリカ人のパトリシアにイタリアに一緒に来るよう説得するためパリへ向かう。その途中、誤って警察官を殺し、殺人容疑で指名手配される。パリに到着すると、ハンスとパトリシアの関係はそれほど単純ではないことがわかります。彼らは映画の大部分を冗談に費やし、ジャーナリストになるというパトリシアの野心は、彼女と一緒にパリを離れるというミシェルの計画に反する。
プロットはパトリシアとミシェルの会話を中心に展開されますが、そこでは二人は常にお互いに話すのではなく、すれ違いながら話しているように見えます。確かに彼らの間には相性があり、一方ではパトリシアのアメリカ人としての側面と、もう一方ではミシェルのフランス人としての、ある種の相互の魅力のようなものがある。しかし、実際に対話しようとしても、どちらも相手の気持ちが本当に伝わりません。あるいは、ミシェル自身が言うように、「私たちが話しているとき、本当はお互いのことを話すべきなのに、私は私のこと、あなたのことについて話してしまいました。」
連続性の原則に従わない型破りなカットは、ミシェルとパトリシアがお互いに到達する際に抱えている問題を効果的に示しています。同時に、伝統的なフランス社会に適合しないミシェルが、アメリカ的なものをすべて取り入れて新しい文化的、社会的アイデンティティを簡単に取り入れることができないことも示しています。代わりに、彼はその中間にある第 3 の道にたどり着きますが、それは長期的には持続可能ではありません。ミシェルのような人物の居場所はまったくない。
プロットは伝統的な因果関係のパターンに従っていませんが、『最後の息まで』はゴダールの映画の中で最も親しみやすいものの 1 つです。この作品は、彼のその後の映画ほどあからさまに政治的でもなければ、ひねくれて非合理的でもありません。「トクストーレン」または「赤字の中の遠足」、しかしそれに比べて、現代のパリのより現実的な基盤があります。 『ティル・シスタ・アンデタット』の政治的側面は、むしろこの映画に政治性が存在しないことにある。ミシェルのよそよそしい態度と、自分の利益や楽しみを増進しないものには無関心な態度は、社会の裏切りによる世代全体の疎外感を象徴している。その点でも、「To the Last Breath」はフランスのニューウェーブと、それが生まれた激動の時代を象徴しています。たとえば、それは 1968 年の若者の蜂起よりわずか数年前です。
エマ・ボーネルランド