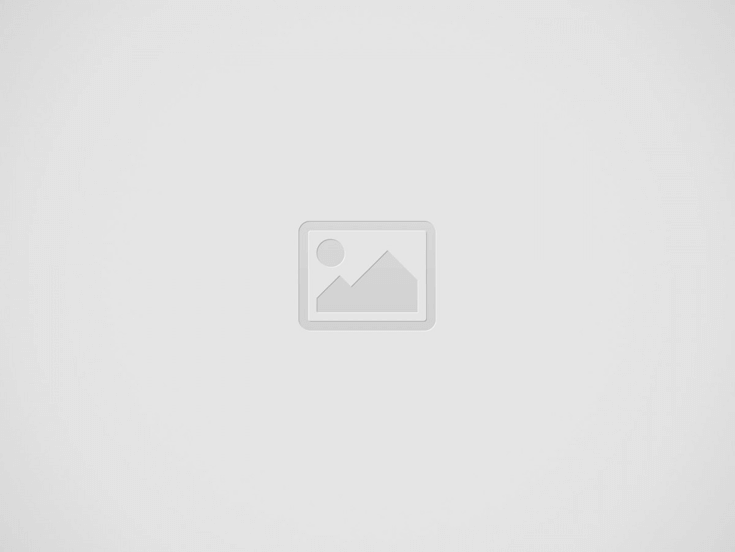ラース・フォン・トリアー監督が深く混乱した連続殺人犯を演じると、被害者の体の一部のように意見が分かれるだろう。面白く、恐ろしく、同時に哲学的であることを目指したスリラーですが、結局は効果ばかりを求めて退屈になってしまいます。
2011年にこの映画に関する発言で禁止処分を受けていたラース・フォン・トリアー監督が、猶予を持ってカンヌ映画祭に復帰すると、ヒトラーは予期せぬカムバックを果たした。しかし、『ジャックが建てた家』は第二次世界大戦の映画ではなく、同様に混乱した連続殺人犯を描いた、病的に混乱したスリラー。一方、監督は再び哲学者を演じようとしており、芸術、歴史(ヒトラーとスターリン)、政治に至るまであらゆるものが大学の講義のようにさまざまなピクチャーコラージュを通して議論される会話を中心にアクションを展開している。
会話は、タイトルキャラクターのジャック(マット・ディロン)とヴァージ(ブルーノ・ガンツ)という名前の未知の男によって進行され、ジャックが犯したさまざまな女性(そして子供たち!)の殺人へとつながり続けます。彼は、それらは異なる形式の芸術であり、映画の観客はそれが非常に詳細なシーンでどのように作成されるかを知ることができると主張しています。ダンテの「インフェルノ」のパロディである可能性のあるシークエンスも登場する予定だが、これらすべてが実際にどのように結びつくのか、そして物語の目的が何なのかは依然として不明のままだ。
映画の中で取り上げられている、芸術や映画についての道徳化には注意が必要ですが、『ジャックが建てた家』に嫌悪感を抱く人がいるのは十分に理解できます。ここには、あまりにも不潔でうんざりするので、ほとんど語ることができないシーンがあります。フォン・トリアーが女性蔑視者としての評判を持っていたことを考えると(彼自身は否定している)、彼がそのイメージを本当に燃やすような映画を作るのは少し奇妙だ。
殺人事件の被害者にはユマ・サーマン、ライリー・キーオ、ソフィー・グラボルがおり、いずれも演技力があり、マット・ディロンは抑制された演技で映画を牽引している。
しかし、「ジャックが建てた家」の大きな問題は、この映画の実際のポイントは何なのかということです。それは真っ黒なコメディ、一種の哲学的な拷問ポルノ、または不気味なドラマとして見ることができますが、共通のスレッドや思想はどこにも見つかりません。
それは純粋な挑発として、技術的によく作られたものとしては実に効果的だが、フォン・トリアーが叩く血なまぐさいドラムの中であまりにも虚しく響く。また、この映画は長すぎて、多くのシーンが不必要に引き延ばされているように感じられ、特に大げさなアートトークが散りばめられているシーンは特にそうです。
「ジャックが建てた家」は議論や議論を呼び起こすだろうが、映画としては、これはラース・フォン・トリアーの中でも最悪の作品の一つだ。