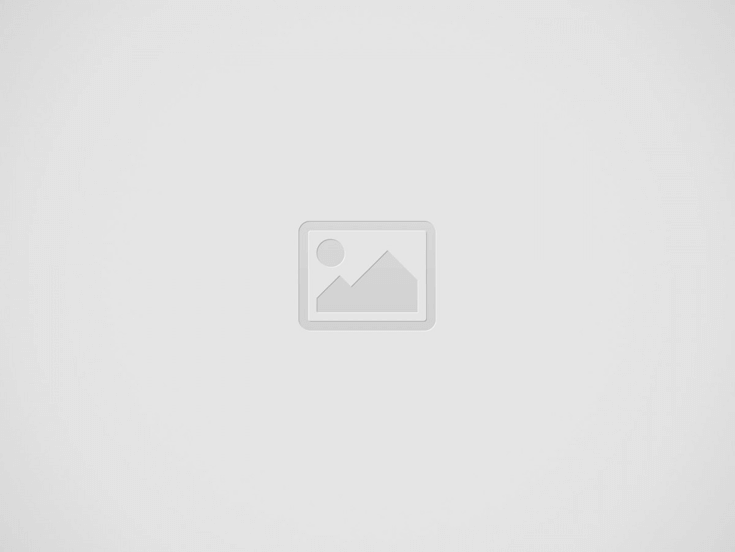レビュー。 『マッド』のジェフ・ニコルズ監督が復帰作として、1960年代のバイククラブを見事に描いた作品となっている。ストーリーに新しい点はあまりないが、ジョディ・カマーはこの映画の輝かしいスターである。
最高のジェフ・ニコルズ(「Take Shelter」、「Mud」) 1960 年代の厳格だが破壊的なオートバイ文化の描写が初期に提示されています。この映画のナレーターは、物語の唯一の女性キャラクターであるキャシーです(ジョディ・カマー)、MC リーグ ヴァンダルズで最も尊敬されるメンバーの 1 人であるベニーの妻 (オースティン・バトラー)。彼女はフラッシュバックで写真学生のダニー・ライオンに語った(マイク・ファイスト)彼女がどのようにベニーと出会い、リーグの浮き沈みを目撃したかについて。
キャシーを映画の主人公に、カマーを主役に選ぶのは、フェミニストの立場でもなければ、この文脈では間違いなくカマーが最強の選手であるという事実に基づくものでもありません。リヨンの写真集に基づいて脚本を書いたニコルズが、これらの傷だらけのMCの男たちの性格とダイナミクスを研究したことは明らかです。
ベニーは、ジェームス・ディーンのコンプレックスを持つ、ワイルドで予測不能な反逆者です。ジョニー(トム・ハーディ)メンバーを家族のように世話する一方で、瞬きすることなく残忍な暴力を命令するリーダー。ブルーシー(デイモン・ヘリマン、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)忠実な部下など。彼らの主な共通点は、自分の感情を頑なに内に秘めていることです。キャシーは早い段階で、ベニーは自分の父親が亡くなったときも泣かなかったと説明しました。
したがって、映画の唯一の女性キャラクターだけでなく、部外者も物語に奉仕する人物になるのは論理的になります。キャシーの恐ろしいリーグに対する視点と見方は、嫌悪、恐怖、魅惑、受容、所属、煩わしさ、そして無関心の間でほぼ常に移り変わります。このようにして、キャシーは、革ジャンを着て大声でビールを飲むマッチョな男たちがいる、この適切に恐ろしい、騒々しい世界に私たちが入るとき、私たちが手を握る安定したヒロインになります。彼女はこの映画の中心であり魂であり、男の子の世界では、誰かが本当の気持ちを話し始めるとすぐに物事が不快になるときに、私たちが共感する鼻の上に皮をかぶった女の子です。
残念なことに、ニコルズはキャシーの視点を放棄することが多すぎて、オートバイクラブ自体の率直な雰囲気を垣間見ることができません。もちろんそれがこの映画の目的だが、語るべき興味深い点、あるいはむしろ新しい点はそれほど多くないかもしれない。他のギャングロールと同様に、忠誠心、名誉、栄光が最も強力なテーマです。多くの場合、ロレーヌ・ブラッコのキャラクターにもっとスペースが与えられていれば、この映画は「マフィアブレーダー」のMCバージョンとして体験できたはずです。
しかし、それはともかく、期待通りのマッチョなメンタリティに加えて、十分な魅力を備えたこのギャングを好きにならないわけがありません。うんざりするが典型的なやる気のない戦いとは別に、彼らの公園でのパーティーでは、心地よく楽しい雰囲気が描かれています(たとえ食事用のカトラリーが不足していたため、署名者はそれほどパニックにならなかったとしても)。
しかし、ここでは、その印象的なアンサンブルが評価に値する――特にメイクアップ・衣装部門は、このよく剃られたハリウッドの巨体を、汚れた汗まみれの豚に変えることに(ほぼ)成功している。バトラーは「エルヴィス」のバリエーションにすぎないが、ハーディは当時と「ゴッドファーザー」の両方のマーロン・ブランドを受け入れるために最善を尽くしている。
ヘリマン、ボイド・ホルブルック(『ローガン』)、エモリー・コーエン(『プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ』)、ボー・ナップ(『ロスト・シンボル』)、カール・グルスマン(『レプタイル』)といった過小評価されている俳優たちが脇役で輝きを放つ。しかし、ノーマン・リーダスをMCヒッピーという最小限の役で出演させる意味は失われている。トビー・ウォレス(『ベイビーティース』)演じる生意気な若者が、まったく深化も発展もしないまま重要な役を得るのと同じだ。常に素晴らしいマイケル・シャノン(ニコルズのすべての映画に出演)の数シーンは、間違いなく監督へのサービスです。
しかし、結局のところ、これは「キリング・イヴ」の主演であるカマーの映画であり、「フリー・ガイ」と「ラスト・デュエル」で男性共演者の影で演じた後、彼女はここで本当にスクリーンを所有することになります。オスカー賞にノミネートされる作品だとしか思えないが、彼女はユーモアと目の輝きを、劇的な重みと真剣さを兼ね備えている。このキャラクターは単なる「心配する妻」、つまり自分自身のために立ち上がる現代の女性を超えたものになります。
ニコルズ監督にとって、2016年の『ラヴィング』以来となる長編映画は、1960年代の忘れ去られた文化をバックミラーに映し、その時代を勇ましく再現する興味深い、演技の効いた作品だ。しかし、潤沢な予算を与えられたインディーズ監督にはよくあることだが、これまでは約15ドルだったのに対し、今回は3000万〜4000万ドルとなっており、作品価値が高まるにつれ、ある程度の感覚は失われていく。素晴らしく洗練されているが、望むほど本物に感じられることはめったになく、不自然な結末も役に立たない。一見の価値があるのは間違いありませんが、近くの MC クラブに参加する気は起こらないかもしれません。