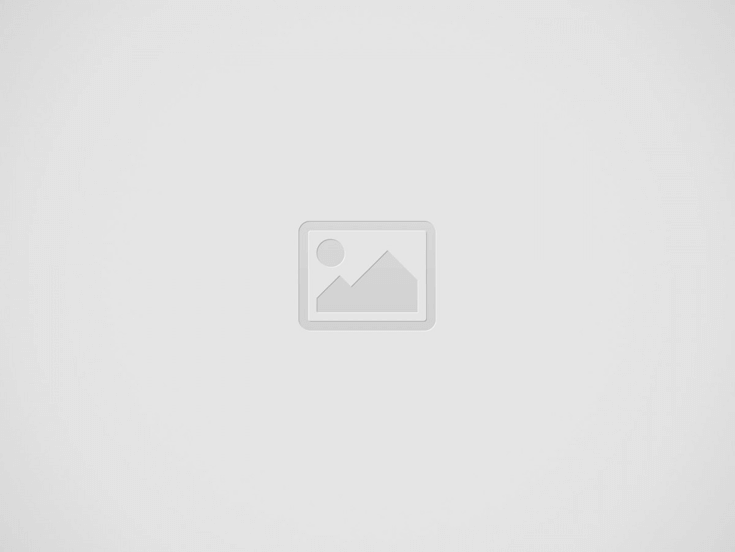天才と称されているが経験の浅い作家カルビン・ウィアー=フィールズ(ポール・ダノ)は、執筆のけいれんをなんとか克服したとき、自信を持ってそうしました。彼の主人公の女性は、不可解にもウィア・フィールドの小説から抜け出し、現実の生活に現れ、彼に深く恋をしているが、彼女自身の非常に文学的な出自には気づいていない。自分が音響的に完全に精神異常者になったわけではないと判断した後(他の人もルビー(映画の脚本家でもあるゾーイ・カザン)と呼ばれる姿を見て交流することができる)、カルヴィンは自分が大当たりだったことに気づく。
彼は今、夢に見た女性と一緒に人生を過ごすことができるだけでなく、彼女が次に何をすべきか、どのように感じるべきかを小説に書くことで、彼女の行動を詳細レベルまで調整する能力も持っています。 「それで、彼女の胸が突然大きくなったと書いて終わりですか?すべての男性を代表して、この機会を逃さないでください!」カルヴィンの悪党(しかし、実際には善良な)兄だと思っています。しかし、そのような極端な話はカルビンには興味がありません。カルビンもルビーが彼から離れる直前までルビーの気持ちを調整し始めません。なぜ彼女がその一歩を踏み出したかったのか理解できます。彼はかなり陰気な人物で、支配的で理想化し、関係において妥協することを望まず、自分自身に満ちています - まさに男性のエゴがそうであるように。
『ルビー・スパークス』のマーケティングにおいて、彼らはこの映画が後任の監督コンビの復帰を示すものであると強く主張している。「リトル・ミス・サンシャイン」、しかし、それをありふれたロマンチックコメディやありきたりのロマンチックなドラマを超えたものにしているのは、ゾーイ・カザンの物語です。不必要な派手さの背後に、愛やパートナーを理想化しようとする人間の衝動、冷める愛、一人になることへの恐怖について、驚天動地とまではいかないまでも、興味深いことが書かれている。
こうした普遍的なテーマは、作家の創作物が現実になるという映画を特徴付けると思われるメタ文学的なテーマの前景で行われることが許されており、それは賢明な選択だったと思います。もしあなたが、甘くてクレイジーなルビー、あるいは彼女が時々物体に貶められてしまうという事実に対して、危険なほどアレルギー反応を起こしそうになっていて、ここでの男性の視線が主に解釈上の優先順位を占めていると思うのなら、あなたは完全に正しいです - 私は想像しますカザンが話したいのは、まさにそのような理想化と単純化の傾向である。