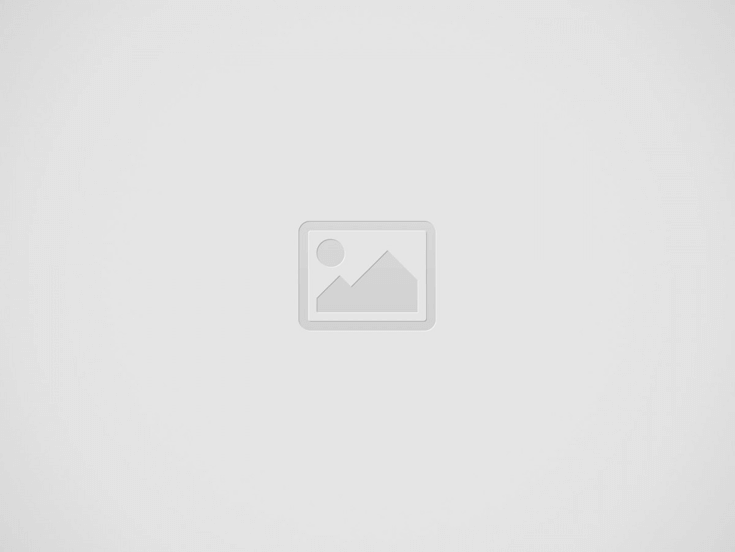ラリー・クラークは映画デビュー作で才能を発揮しているが、1990年代に多くの人々に衝撃を与えた、セックスとドラッグに溺れるティーンエイジャーの物語は、今日でも同じ影響を及ぼしているとは程遠い。その代わりに、やりすぎで、共感も興味も持たない非同情的なキャラクターによってロックが解除されているように感じます。
『キッズ』は1990年代に公開され、多くの人に衝撃を与えた。ここほど無責任かつ無謀にセックスとドラッグに溺れる十代の若者たち――それも若すぎる――を見たことがなかった。さて、この映画は数年前のもので、若者が何を待っているのかをよく知っています。さて、視点から見ると、映画はむしろかなり誇張され、誇張されています。まるで、初監督のラリー・クラークと脚本家のハーモニー・コリンが、若者が危険な行為で自らを堕落させているという認識を叩きつけようとしているかのようだ。
結局、未来への希望が失われるというのがこの映画のオチであるかのように、かなり無意味に感じられる。結末はハッピーでも悲しいでもなく、むしろ無感動な結末だ。物語は本当に悲劇的ですが、登場人物たちはあまりにも同情心がなく、セックス、ドラッグ、暴力を無心に追求する姿はむしろゾンビに似ています。彼らは信頼できるものですが、挑発したり動揺させたりすることを目的としている場合、それは逆にうんざりするものになります。このタイプのティーンエイジャーは、現実にも映画にも参加しません。
ただし、ゲームや演出を責めることはできません。若い流れ星、レオ・フィッツパトリックとジャスティン・ピアース(二人とも残念ながら表舞台から姿を消し、後者は悲劇的に自殺した)は、漂流者のテリーとキャスパーとして完全に本物だと感じている。彼らは、即興ではない会話をリラックスして自然に感じさせ、間違った優先順位を持つ自己陶酔的でよそよそしい10代のデュオの暴露をうまく受け入れています。
デビュー作のクロエ・セヴィニーとロザリオ・ドーソン(後者は、数少ない好感が持てる役の一つだが、時間が限られている)が彼らとともに輝きを放つことになる。しかし、セヴィニーはHIVのメッセージを持った少女として、残忍なラストシーンで正しいことをするための最小限の力が損なわれた被害者のままである。それはあたかも、性的に活発な十代の若者たちをひとまとめにして、自分たちに責任があると言いたいかのようなものだ。 HIV 陽性の同性愛者には、次のようなより緩和的な描写が与えられましたが、「フィラデルフィア」そして「長年の相棒」そのため、ここでHIVに感染した少女は、10代の無責任なセックスの命のない広告塔となる。
実は、この映画は大きな可能性を秘めた映画なのです。クラークというコンビ(彼もまた、10代のセックスをカミソリのような正確さで描いた)「ケン・パーク」)とコリン(後に次のような独自のオリジナル作品を制作しました)「ガンモ」そして最後に"春休み客") は、個々の能力がうまく連携したレーダー ペアです。それは印象的に作られており、才能のある俳優によってうまく演じられています。しかし実際のところ、『キッズ』は発売から20年近く経ったにもかかわらず、あまり古さを感じていない。私たちは、ティーンエイジャーが薬物を使用したりセックスをしたりすることを知っています。メッセージを伝えるのにガッツポーズは必要ありません。それから、次のようなより強力で魅力的なドラマがあります。「十三」そして「痛みの閾値」頼ること。 「子供たち」は、それが属する1990年代に安らかに眠るべきです。