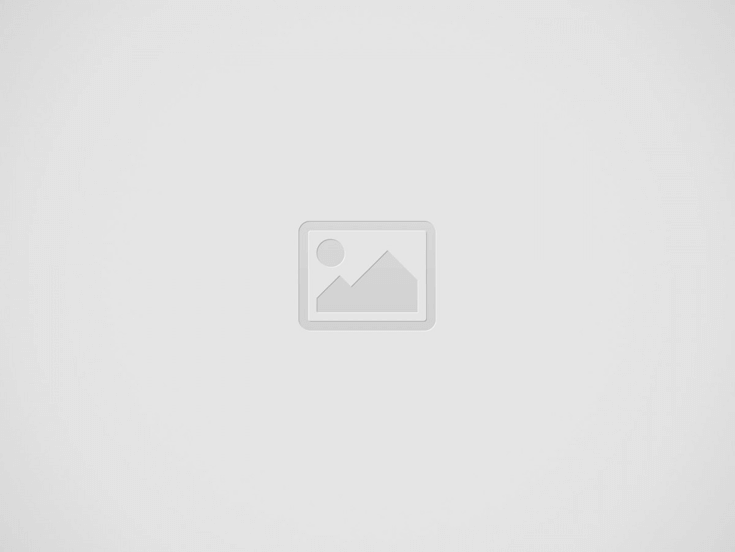ストリンドベリの有名な同名のドラマの映画化で成功した作品。 「ジュリー」は、激しさと信じられないほど優れたパフォーマンスで勝っていますが、終盤の躁鬱の揺れで何かを失い、視聴者を少し疲れさせます。
上流階級の少女ジュリーの真夏の夜の夢と執事ジャンとの冒険は、いつものようにうまくいかないまま終わる。おそらく、権力、階級、性別については少し誇張されている(またはそうでない?)かもしれません。ジュリーはジーンと遊ぶが、結局は弄ばれる側になる。ヘレナ・バーグストロム版のプロットは 1930 年代後半に設定されていますが、それ以外の点はほとんど同じです。城のキッチンで、ジーンの婚約者クリスティンが沈黙の証人として夜のドラマが繰り広げられます。
私は以前、特に女性が近代化されることを間違いなく期待していましたが、クリスティンも私が見慣れているよりも顕著な立場で前に出ているので、確かに何かが起こりました。そして最高の映画。
「ミス・ジュリー」は今年ストックホルムの市立劇場で同じ俳優、同じ演出家によって上演されたが、彼らが団結力を持ったユニットであり、互いとテキストの両方に快適であることは注目に値する。しかし、最初は、ストリンドベリの非常によく明瞭に表現されたセリフが不均一に跳ね返り、私たちが現在扱っている親密な表面を考慮すると、少し大声で発音されすぎますが、映画が少し始まると、もうそんなことは考えなくなり、最終的に言葉は正確に正確になります。そして彼らはそこに着陸するでしょう。
ジュリー役のナジャ・ミルミランは自然でとても信頼できるが、残念ながらキャラクターの表現が不足しており、ヘレナ・バーグストロムには映画の可能性をもっと活用してもらい、もっと彼女に近づけてほしかったと思う。 、タイトルが約束しているように、「ジュリー」。 「ミス」はなくなったが、それでも私は彼女と完全に仲良くなることはなく、私が望んでいたような同情も感じていない。
イェンス・フィッシャーによる撮影はとにかく素晴らしく、ほとんど恥ずかしげのないクローズアップの数々は、時折イングマール・ベルイマンと父グンナー・フィッシャーの素晴らしいカメラワークを思い出させます。また、この映画が本当に命を吹き込むのは、これらの美しい映像の中にもあります。それ自体の。パフォーマンスの前半とその中で続くジャンとジュリーの芝居には夢のようなきらめきがあり、その後現実が二人に追いつくと突然、より自然で冷たい光に置き換わります。これは非常にシンプルですが効果的であり、テーブルの中央にあるストリンドベリのランプを点灯し、映画の残りの部分に余波の外観を与えることが許可されています。これは、思い出させ、ささやかな賛辞として(おそらく)すべての背後にある著者。
そしておそらく、この作品は今日でも観客に十分価値がある作品だろうが、たとえ最後のほうで「嫌い、いいえ、愛してる、いいえ、嫌い、いいえ、愛してる」の繰り返しと揺れが多すぎるとしても...疲れ果てて、特にジュリーとビョルン・ベングトソン演じるジーンの間のエネルギーと相性が物語を救ったとしても、その後の口の中にわずかに苦い味が残ります。ようやくミス・ジュリーが比較的新しい映画に出演することになった今、地下室のキッチンで何年も言い争いを続けてきた彼女(作品)が、当然受けるべき変化と再生をまだ受けていないのは悲しいことだ。ストリンドベリのランプの光のせいで変化が妨げられているのではないかと私は思うが、実際のところ、今日の背後にいる人はそれを歓迎しただろうと私は思う。