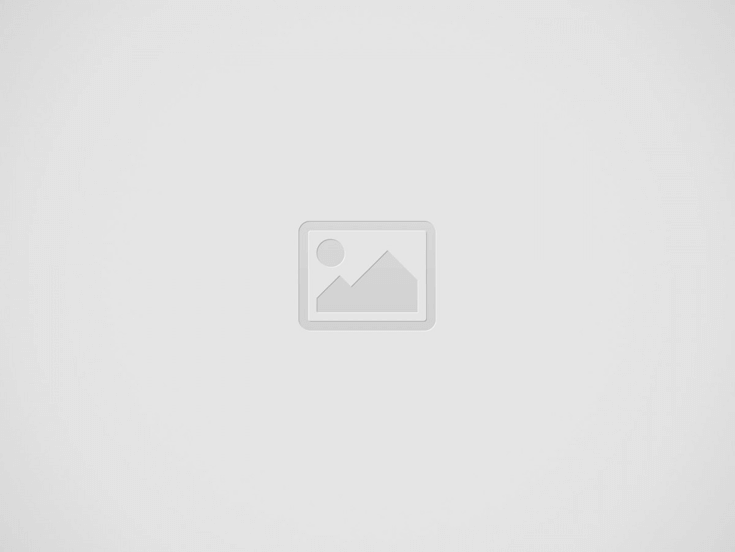おそらく歴史上最も再現された写真は、1945 年 2 月 23 日に太平洋の硫黄島で撮影されたもので、6 人のアメリカ兵がスラバチ山の頂上に星条旗を掲げた写真です。このイメージは即座にアメリカ人の自己理解と神話形成の一部となり、何百もの新聞や雑誌に掲載されました。その後、バージニア州アーリントンにある有名な海兵隊戦争記念館に常設されることになりました。
この写真が「硫黄島に旗を掲げる」ことは、今でも米国でその象徴的な地位を保っています。これは、特にクリント・イーストウッド自身がその背後にある物語を引き受けているという事実によって証明されています。 『父親たちの星条旗』は、ジェームズ・ブラッドリー(写真は海兵隊員のジョン・ブラッドリーの息子)の同名の本の映画化である。
物語は、島での戦闘と、写真に写っている生き残った3人の兵士が後に送られる戦争証書に署名してもらうためのツアーの間を行き来する。戦争の残忍な現実と、英雄を崇拝したいが、彼らが本当は誰なのか、彼らがどんな忌まわしい経験をしてきたのかを見たり聞いたりしようとしないアメリカとの間には、激しい衝突が起こるだろう。
このコントラストが可能なのは、『父親たちの星条旗』には、少なくとも私が映画で見た中で最も汚く、最も不快な戦争シーンがいくつか含まれているという事実のおかげです。 1945 年 2 月の硫黄島は、人が最後に行きたくない場所のように感じられます。機関銃は水際で下船する兵士の階級を次々と機械的に粉砕する。砲撃が轟く中、切断された腕、足、頭が空を飛び、戦いに負けると日本兵は口に手榴弾を詰め込んで自殺を始める――すべてが徹底的に文書化されている。 「父親たちの星条旗」は気の弱い人向けの映画ではありません。
しかし、映画の後半が機能するにはリアリズムが必要です。 3人の兵士が突然アメリカに来て、誰もが突然握手をしたり陰謀を企てたりしたがるとき、彼らの絶望感と消極性の高まりは信じられないほど理解できるものになります。アイラ・ヘイズ(アダム・ビーチ演じる)は最悪の状況に陥る。インド人である彼は、本国の人々が抱く「本当の」英雄のイメージには当てはまらず、人種差別攻撃はますます粗暴なものとなっている。彼は結局、自分の希望もあって前線に戻ることになる。
ヘイズの運命は『父親たちの星条旗』の中で最も感動的で興味深いものであり、この映画はヘイズの視点から語られれば有益だったろう。今では代わりに、もっと当たり障りのない、しかし白人でプロテスタントのジョン・“ドク”・ブラッドリー(ライアン・フィリップ)が主人公となっている。クリント・イーストウッドは確かに、この本に忠実でありたいと言って自分を弁護しているが、ここで彼は英雄主義についての議論を熱く、今日でも意味のあるものにする機会を逃している。いささか不愉快な結論は、アメリカ先住民の英雄を米国に登場させることはまだ完全に実現可能ではないようだということである。 『父親たちの星条旗』も反戦映画と戦争映画の間で揺れ動いており、リアルで威厳に満ちた戦闘描写が前者を、英雄的なレトリックが後者を物語っている。
目的がやや不明確であるにもかかわらず、『父親たちの星条旗』は悪い映画ではない。ストーリーテリングには優れた推進力があり、演技は申し分のないもので、1940年代のアメリカを詳細に再現した控えめに言っても贅沢な演出が施されています。ありがたいことに、私たちは戦争シーンでは最も肥大化したハリウッド音楽も避けています。よし、クリンタン、今回は良い成績を収めたね。しかし、英雄主義について何か本当に興味深いことを言いたいのであれば、次回は第二次世界大戦よりも物議を醸し、あまり馴染みのないテーマに取り組むほうがよいでしょう。なぜイラクについての映画を作らないのか?