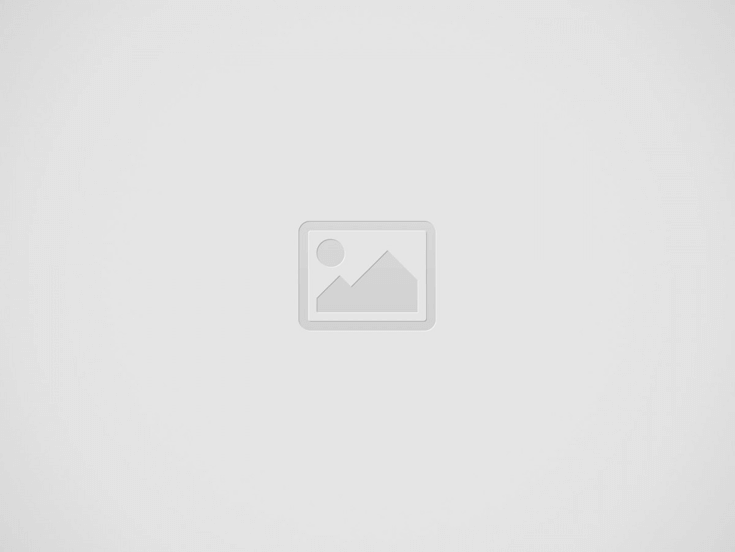いいえ、すべてがうまくいくわけではありません。ヴィム・ヴェンダースが7年ぶりに長編映画に復帰するとき、その間に彼はとりわけ壮大なドキュメンタリー「Salt of the Earth」を制作してきたが、それは3Dテクノロジーとキャラクター主導のドラマを組み合わせるという野望を持っているからだ。宣伝資料によれば、この物語は悲しみ、許し、創造の条件についてのものだという。控えめに言っても、それは賞賛に値することだと思います。しかし、ご存知のとおり、理論と実践を組み合わせるのが難しい場合もあります。
ジェームズ・フランコは、誤って子供を轢いてしまう自己陶酔的な作家を演じています。ヴェンダースは、このトラウマが主人公のその後12年間の人生にどのような影響を与えるのかを3Dで描き、ギャスパール・ノエ(「イレバーシブル」「エンター・ザ・ヴォイド」)の銃所持者でもある巨匠写真家のブノワ・デビエとともにカメラの後ろで撮影した。視覚的には非常に美しく、常に美意識を持ったヴェンダースとデビーは光と雰囲気を巧みに使い、雰囲気のある音楽を求めてヨーテボリ交響楽団(!)を頼りにしています。
その後、さらに複雑になります。 「エヴリ・シング・ウィル・ビー・ファイン」のストーリーが複雑に展開していく中で、ほぼ同等に妥当な解釈が 2 つ思い浮かびます。ヴェンダースも自分がどんな映画を作っているのかよくわかっていない。純粋なスリラー要素は、フランコの非同情的な作家がさまざまな恋愛関係に出入りし、絶賛された本を出版しながら、オスカーの司会を彼にしたのと同じ眠そうな「存在感」と苦悶の表情を交互に繰り返す、ゆっくりとしたペースで長引くエピソードと混合されています。一回限りのイベント。常に注目を集めているシャルロット・ゲンズブールは、死んだ少年の傷心の母親を演じていますが、彼女のキャラクターはフランコを殺した犯人をすぐに許すため、2人の間に探求すべき摩擦はほとんど残されていません。ある時点で、彼らは関係を始めようとしているように見えます。この線路も廃線となっている。亡くなった少年との間の悲劇も、フランコが何度も何度も私たちに困難を感じると語っているにもかかわらず、フランコの作家性と結びついているようには感じられない。
または!それどころか、ヴィム・ヴェンダース監督は脚本(ビョルン・オーラフ・ヨハネッセンが書いた)の質の低さを断固とした態度で指摘しているが、彼は別の問題については反対しており、映画の決まり文句の多いストーリーは、奇妙で曖昧で不気味な物語の背景を形成しているだけだ。一種のソシオパスの拡散性格研究。 「エヴリ・シング・ウィル・ビー・ファイン」は、罪悪感や自己赦し、創造の条件などについてはまったく描かれておらず、人生の愛と献身的な努力を犠牲にして人生を切り抜けようとする、感情的に損なわれた人生を抱えた、取り乱した男の物語である。パートナー。映画の後半には、間違いなく同様の方向、主人公を病理化したいという願望を示すシーンがあります。
しかし、ここには第三の解釈が可能になるほどの両義性も存在する。つまり、ヴェンダースは、自分が自由に使えるあらゆる手段を使って、悪い脚本を救おうとすること以上に手の込んだ計画を立てていないし、特定のシーンが示唆する深さは単に過剰な結果であるにすぎない。テキストでは対応できない意味を持つイベントを読み込むためのディレクター側の努力。
いずれにしても、ヴィム・ヴェンダースの野心的なプロジェクトはうまくいきません。そこには、影に隠れて、3D メガネをかけても見ることのできない、決して解放されない火花である生命が存在します。