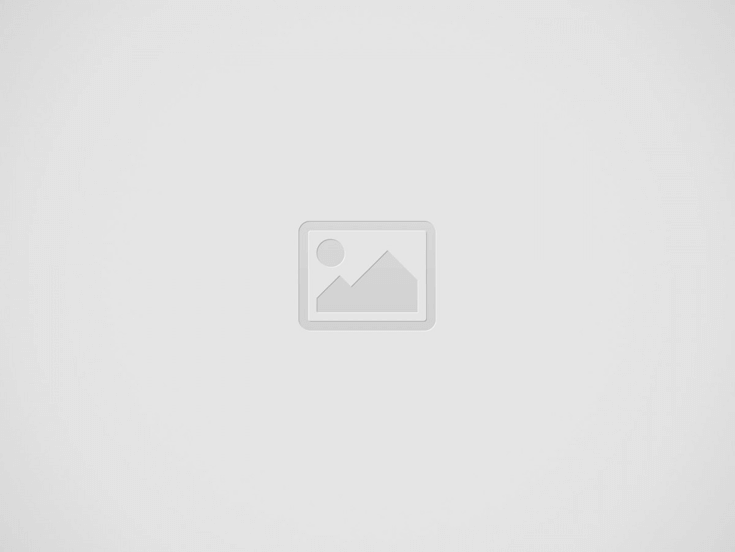1999 年の低予算ヒット作の森の魔女が帰ってきて、カメラを手にしたばかりの若者たちを悩ませています。この映画には決まり文句がないわけではなく、走ったり叫んだりするシーンが過剰に登場しますが、その神秘的な音が森の暗闇の中で鳴り始めると、時々本当に怖くなります。
『ブレア・ウィッチ』は、約 20 年前のカルト映画の続編で、良くも悪くも非常に伝統的なホラー映画です。若者グループは、グループの一人の妹がそこで失踪し、地元住民も標識も恐怖を警告しているにもかかわらず、幽霊が出るとされる森を訪れることになります。謎の音を調査するために人々が一人ずつ出発すると、グループは分裂します(「すぐに戻ります!」)。当然、雨も激しくなり、雷も鳴っています。
同時に、映画館の椅子の腕にますます強くひっかかり、映画がゆっくりと進んでいく間、本当に怖くなってきます。監督のアダム・ウィンガードと脚本家のサイモン・バレット(『ユーアー・ネクスト』と『ザ・ゲスト』を共同制作)は、オリジナル映画の当時画期的だった雰囲気を取り入れ、震える手持ちカメラと懐中電灯で森の暗い隅を必死に探す緊張感を生み出した。私たちが恐れているものを見せず、それによって頭の中に悪夢のイメージを作り出すことは古典的ですが、それでも効果的なトリックです。
ウィンガードとバレットのコンビが真のホラーファンであることは疑いの余地がありません。 「ブレア・ウィッチ」は、他のほとんどのファウンド・フッテージ映画よりも生々しく、大音量で刺激的で、最新のテクノロジーを使用するとさらに見栄えが良くなります。フィナーレは、よくできたコンピューター ゲームと、観光客向けのお化け屋敷への現実の訪問を組み合わせたようなものです。懐中電灯と雷の光が街角で恐ろしいものを垣間見せながら、地獄のお化け屋敷を全速力で進んでいきます。 。
しかし、ストーリーテリングは映画製作者の得意分野とは言えません。明らかな決まり文句に加えて、一連の手がかりや詳細が提示されます(たとえばドローンなど)が、結局のところ本当の意味を欠いています。面倒なことに、あなたは、人の後ろに忍び寄って半分怖がらせると、実は無害な友人だったことが判明するような、不必要な「偽の恐怖」をいくつか使ってペースを維持しようとします。まるで幽霊の森にいるかのように。
また、恐怖を少し引き延ばしすぎて、映画が実際よりもはるかに長く感じられます。時々、走ったり、叫んだり、這ったりすることにうんざりすることがあります。興奮と疲労が交互に起こります。しかし、お化け屋敷を訪れるのと同じように、少し震えながらサロンを出なければならないので、やはり怖いです。すべてを完全に考え抜いてはいけませんが、ちょっとした寒さを体験したいなら、ホラー アイスクリームが最適です。二度と森でキャンプしたくなくなるでしょう...